病気のはなし
不登校の支援について
はじめに
文部科学省による調査では、小中学生における不登校の児童生徒の割合はコロナ禍前の2013年以降より増加の一途をたどり、2023年度には中学生の6.7%が不登校とされる深刻な状態となっています。その背景に関しては様々な議論があり、明確な結論を出すことは難しい状況ですが、長期にわたる不登校の状態が子どもに与える影響は少なくなく、子ども達にとって1つの逆境といっていいように思います。
今回は逆境にまつわる児童青年精神医学領域における研究結果を参考に、不登校の支援について考えてみたいと思います。
逆境にあって子ども達を守る体験(保護的・補償的体験)
児童青年精神医学領域の研究では、小児期や思春期に体験した虐待などの体験(逆境的小児期体験)が積み重なると、大人になってからの精神的健康や身体的健康に悪影響をもたらすという数多くの報告があります。一方で、一連の研究からは、逆境にあっても子ども達を守る10種類の体験(保護的・補償的体験)の存在が明らかになっています(表1)。
(表1)保護的・補償的体験
②親友がいること
③コミュニティにおけるボランティアに参加すること
④集団の一員であること
⑤メンター(信頼でき、助けやアドバイスを頼りに出来る親では ない大人)がいること
⑥清潔で安全で十分な食べ物がある家に暮らすこと
⑦教育を受けること
⑧趣味を持つこと
⑨身体的に活動的であること
⑩ルールと規則正しい日課を持つこと
これらの体験は、虐待などによる悪影響をやわらげる術を求める中で見出された体験であり、不登校の支援にはあてはまらないように思えるかもしれません。しかし、実際に不登校の子ども達の支援を行っていますと、これらの体験が不登校からの回復のきっかけになることは珍しくありません。
子ども達の支援にあたっては、(表1)を眺めながら、今の状況で可能そうなことに取り組んでみるとよいと思います。ここでは紙面の都合もあり、これらの体験の中でも支援の土台といえる無条件の愛について紹介します。
無条件の愛について
無条件の愛は、子ども達が自分の行動の善悪を抜きに愛されていると実感していることを指し、これが温かみと適度なルール設定のある望ましい育児の土台となるものです。
学校にいけなくても、自分が大切にされ、尊重されていると子ども達が感じるようになると、ぽつぽつと親子の間に温かみのあるやりとりが回復し、次のステップへとつながっていきます。
表1の他の項目は既に試したけれどうまくいかず、不登校が長引いてしまっている場合には、子ども達だけでなく保護者自身も疲れ切ってしまい、無条件の愛どころではなくなってしまっていることがよくあります。行き詰まった際は、まず保護者自身がいかに回復するかが重要といえます。
保護者自身が回復するために
先ほどご紹介した保護的・補償的体験は、大人にとっても役立つ可能性が示されています。表1を眺めながら、ご自身のために出来そうなことを探してみることも子ども達の回復につながります。
現在、不登校に関しては、教育相談センターや子ども家庭支援センターを始めとして様々な相談の場がもうけられています。まずは保護者の方自身が支援につながることからはじめてはいかがでしょうか?

おわりに
お子さん達の支援に携わっておりますと、親子ともども何をどうしたらいいかわからなくなってしまった時こそ、焦らず、急がば回れといった心持ちで取り組んでいくことが重要であると感じます。精神医学領域における回復は、前の状態に戻ることではなく、より自分らしく生きられるようになっていく過程を意味します。
手間暇はかかってしまいますが、保護者の方もサポートを受けながら、少し手を伸ばせば届きそうな体験を子ども達とともに大事に積み重ねていくこと、それが遠回りに見えて一番の近道といえると思います。
参考文献
●文部科学省初等中等教育局児童生徒課:令和5年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について. 2024.
●ジェニファー・ヘイズ=グルード,アマンダ・シェフィールド・モリス(著)菅原ますみ,榊原洋一他監訳:小児期の逆境的体験と保護的体験 子どもの脳・行動・発達に及ぼす影響とレジリエンス.明石書店, 2023.
詳しくはこちらの診療科にて
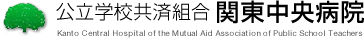

 採用情報
採用情報 研修医募集・病院見学
研修医募集・病院見学 組合員専用
組合員専用 パンフレットダウンロード
パンフレットダウンロード