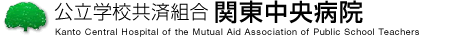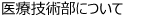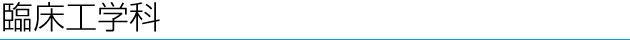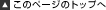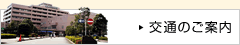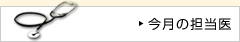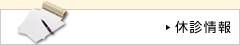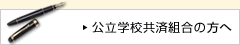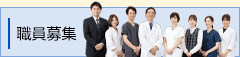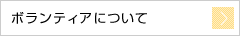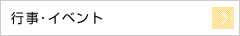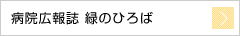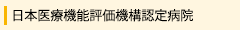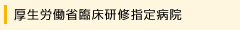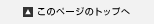臨床工学技士の業務
臨床工学技士の業務は「生命維持管理装置の操作・保守点検」となっていますが、一口に「生命維持管理装置」といいましても多種多様にあります。
生命維持管理操作を行うためには専門知識や手技操作の習得が必須となる為、研修や勉強会に参加することで安全な業務遂行に務めています。
当院では、2021年より循環器部門と血液浄化部門の2部門に分け、各部門に一人専任の臨床工学技士を置き、その他の臨床工学技士はローテーション制度をとることで幅広い業務に対応できるよう努めています。
また、365日24時間オンコール体制をとっており、緊急時の心臓カテーテル検査、補助循環、急性血液浄化も対応しています。
現在スタッフは7名で以下の業務を行っています。
血液浄化部門
2023年5月より外来透析は月水金、火木土とも1クールに変更しております。(1クール最大10床、うち1床隔離透析可)
入院透析は1クールまたは2クールに行っております。透析治療としては、HD、オンラインHDF、IHDF全て対応可能でおり、血漿交換、血漿吸着、直接血液還流(主にGCAP、PMX)、腹水濃縮還流(CART)も施行しています。


循環器部門
手術室業務、カテーテル業務、ペースメーカー業務、集中治療業務、機器管理業務、を分担して行っています。
手術室業務
手術室で使用する生命維持管理装置は人工心肺装置や麻酔器があります。
心臓と肺の機能を代行する装置が人工心肺装置です。
心臓外科の手術では心臓を止めて手術するものも多く必要不可欠な医療機器になります。この人工心肺装置の管理、操作を行っています。
全身麻酔で必要不可欠な機器が麻酔器です。麻酔器の始業前の点検を毎朝おこなっています。
手術室には生命維持管理装置の他にも各種モニター、自己血回収装置、超音波メス、除細動器など多くの医療機器が存在します。
安全に手術が行えるように手術室で使用する医療機器の管理、点検を行っています。

カーテル室業務
心臓カテーテル検査、治療では手技中の心電図変化や血圧を記録するポリグラフの操作、冠血流予備能検査時の機器操作、治療の時に使用する血管内超音波の操作を行っています。また心筋梗塞や不安定狭心症に対する緊急カテーテルに対応するためオンコール対応を行っています。
他にも頻脈性不整脈を治療するカテーテルアブレーションでは、多くの特殊な機器を使用します。臨床工学技士は3Dマッピング、心内電位解析装置、心内電気刺激装置、高周波発生装置等の操作および介助を行っており、より安全な治療を提供できるよう務めています。


ペースメーカー業務
ペースメーカー植込みや電池消耗によるペースメーカー交換時にはペースメーカーの設定を行う装置(プログラマー)の操作を行っています。
ペースメーカーを植え込まれている方の入院や手術があるときは、医師と相談しペースメーカーのチェックや設定変更を随時行っています。
ペースメーカーを植え込まれている方のMRI撮像時は医師とともに立会い設定の変更を行っています。
当院でペースメーカーを入れられた方を中心に第一、第三金曜日にペースメーカー外来を医師と共に行っています。
集中治療業務
集中治療室では多くの医療機器を使用します。
生体情報モニター、ポンプ類、人工呼吸器、補助循環装置、血液浄化装置などを使用し患者さんの状態管理を行っています。
これらの医療機器が集中治療室で適切に作動しているか、異常がないかを日々ラウンドしています。


機器管理業務
医療機器を安心して使用するため、使用後の点検、定期的な点検を行っています。
また院内では多くの医療機器が使用されるため故障や機器のトラブルが起こり得ます。医療機器の異常や故障が発生した場合は点検や修理を行い、院内で対応できない場合は医療機器メーカーに連絡を取り素早い対応を心がけています。
機器管理室では輸液ポンプ、シリンジポンプ、低圧持続吸引器、人工呼吸器を中央管理し、病棟で使用している機器の故障やトラブルの対応を随時行っています